
ここで、京都府乙訓郡大山崎町の「ibuki」という家具修理業を紹介する。
代表は一柳恵亮氏、42歳である。(個人事業所)
一柳氏は同業種での修行から、2015年に独立した。創業以来、地道に雇用者数と売上を成長させている。創業当初の入社希望者が女性が多かったので、女性のみの現場となった時期もあった。
この事業所の立地は、阪急 大山崎、JR山崎から徒歩20分はかかるという条件の恵まれない立地である。本事業所に関して、当職は開業以来、労務管理面でのかかわりが多く、社員の成長する過程も見てきた。
一柳氏は、この修理業をひとつの技術として捉えて、社員にもそれを伝授しようという熱意がある。社員は社歴を重ねその技術を身に着けていく過程で、明らかに自信のある顔に変わっていく。
まず、取り組んだのは社員として入ってきた者への補修技術の訓練で早期の戦力化を目指した。今まで、正社員になったものは一人目の正社員以外は漏れなくこの訓練を通過している。(事業を止めてのトレーニングなので、制度上、最初の社員は適用出来ない)。
これはOFFJTとOJTを交えた厚生労働省の支援施策であるが、本来、職業訓練センターのするべきことを民間活用している形である。訓練時間の受講生の人件費がバックされるシステムで、外部講師活用などでかかった経費は補助される。先輩のやり方から盗めというのはもう時代遅れである。また、仕事の体系が分かるまでどの部分の仕事をになってているのか分からず迷うケースが多いからである。
その事業所側にはこれを機会に技術を棚卸するという副次効果もある。
最近では、OJTの方は先輩社員が指導役を受け持つ形を取り、社内でのしっかりとした技術伝承の形が出来ている。OFFJTの方は、10年間の同業種経験年数が必要なので、事業主の
一柳氏自ら教えている。(OJTカリキュラムと評価表は次ページ参照)
これ以降取り入れた施策のメリット・デメリットを上げる。
陽の側面 技術の習得に伴って、仕事をしている実感が自信につながる。
影の側面 新卒を含む若い世代は日々の訓練日誌を書くだけで時間を要する。それで悩むケースもある。極端な事例では当初に訓練カリキュラムを見た瞬間に習得困難を感じて会社を辞めるケースさえある。(これは他社事例)
このケースは、適性が早めに分かったと割り切れば、デメリットにはならない。
.gif)
上が訓練カリキュラムの内OJTの内容、下は訓練終了時につける評価表で、自己評価と企業評価がある。通常、正社員化にはA・B評価が8割以上などの歯止めをつける。
近年、在学時代に借りていた奨学金が社会人になっても尾を引いている社員がいる。
‘ibukiはそこを手当として一定期間、支援する制度に取り組んだ。
奨学金返済手当制度の定義とは、大学・大学院・短期大学・高等専門学校。専修学校(専門課程)高等学校卒業者(中退者も含む)であって、奨学金返済中のものに対して支給するものである。その手当額の一定分を支援金として補助する行政支援の仕組みもあった。
京都府でも奨学金支援している会社をサイトに掲示してくれるなどの恩典もあった。
陽の側面 会社としていかに社員に寄り添っているかを示すことができ、社会貢献面での知名度も上がる。また、制度利用の既存社員からの入社志望者の紹介にもつながる。
影の側面 本来、給与とは労働(能力)が反映されて決まるもので、異質な要素が入ることになる。具体的には同期入社したものの間で、将来の年金に反映される標準報酬がこれによって差ができることになってしまう。
これは、ibukiの施策をトータルで見ても技術を縦軸で通している中では本旨策は多少浮いていた面はある。制度活用の該当の社員は結局、人生の方向性の違いから(円満)退職に至っており、本制度が社員をつなぎとめるものではないことも分かった。
*新著の配付書店一覧表
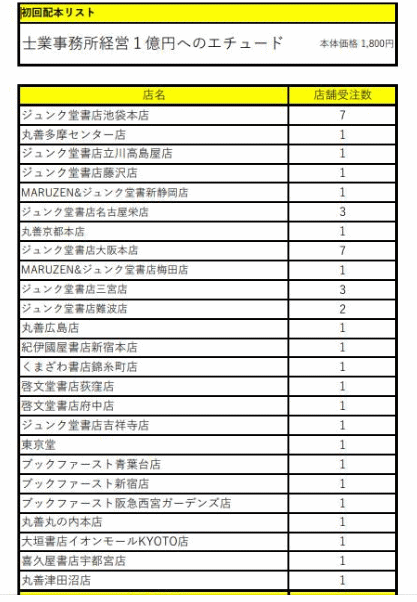
*サイト申し込みはこちら
「士業事務所経営 1億円へのエチュード(練習)」
〜スケールの全軌跡〜

西河 豊 著 株式会社西河マネジメントセンター 監修
1,980円(税込み)三恵社 申し込みはここ