
直近の戦略を知的資産経営報告書の形で公開します。 ここ
7.経営革新計画
経営革新法の神髄は事業所の強みを生かしてそれをバージョンアップして市場に乗り出すというもので、まったく世になかった発明に近いものを出せという意味ではありません。
過去に、創造法というそれに近いものがあって、特許とともに申請するというのが普通でしたが、マーケットで売れませんでした。
そこで、経営革新法の新規性の定義は「県で初めて、あるいは業種で初めて」とされています。
しかも、やり方としての新規性でも良いのです。
この考えは事業再構築補助金まで引き継がれていますが、新規性の捉え方で勘違いしている事業主は多くいます。
繰り返します。発明ではないのです。
もう一つエポックメイキングな出来事は初めて付加価値額という指標が登場したことです。公式は以下に説明していますが、人件費と減価償却費を足し戻して、リストラでは申請が出せない形にしたのです。
以下形式要件です。
・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
経営革新計画の要件
(1)新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発及びその成果の利用
(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること
経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。
計画期間
経営革新計画の計画期間は3年間から5年間です。
(計画期間については、新事業計画に応じて各企業で設定してください)
経営指標の目標伸び率
経営革新計画は、「経営の相当程度の向上」を図る計画であることが必要です。
「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。承認には、条件①と条件②の両方を満たす必要があります。また、目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。
計画期間 条件①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 条件②給与支給総額の伸び率
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
条件①(付加価値)条件②(給与総額)
3年計画 9%以上 4.5%以上
4年計画 12%以上 6%以上
5年計画 15%以上 7.5%以上
以下個人事務所時代の経営革新法申請書式ですが、
・別表1のプランの内容書くところが重点的に見られて、それ以外の別表2 行動計画、別表3 資金計画はあまり問題とはなりません。審査する人もいかようにも書けると思っているからです。
プランの新規性についてはネットで類似業者の情報をリサーチされると思ってください。
事前準備で、提出側もこのリサーチを漏らしてはいけません。
知らないところで、同じアイデアを出している人は意外といるものなのです。
別表7は認定後の公表項目ですが、研究開発系ではテーマ明さえ隠しているケースもあります。
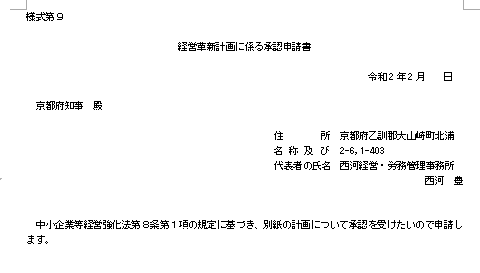
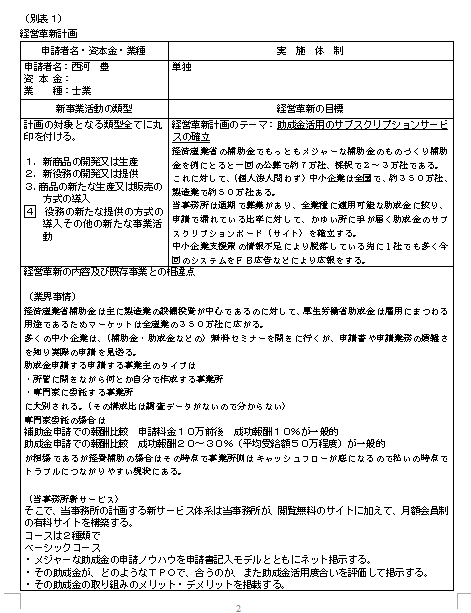
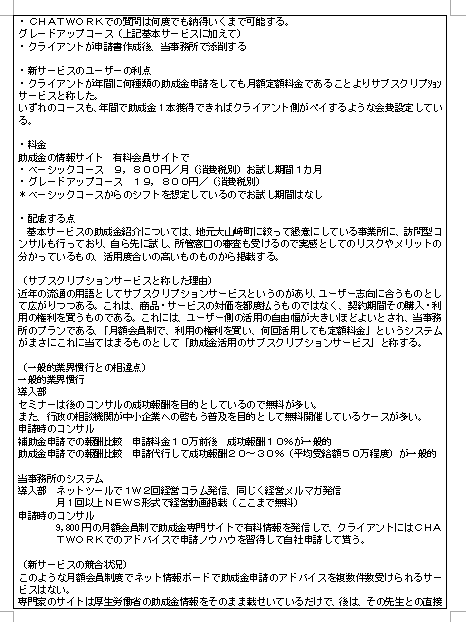
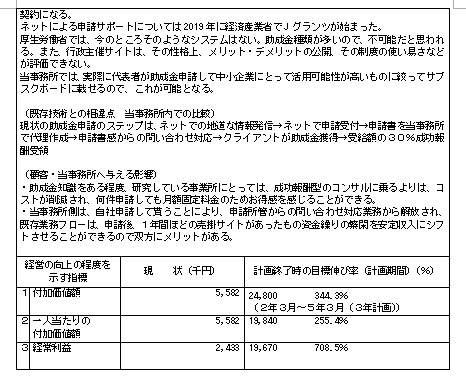
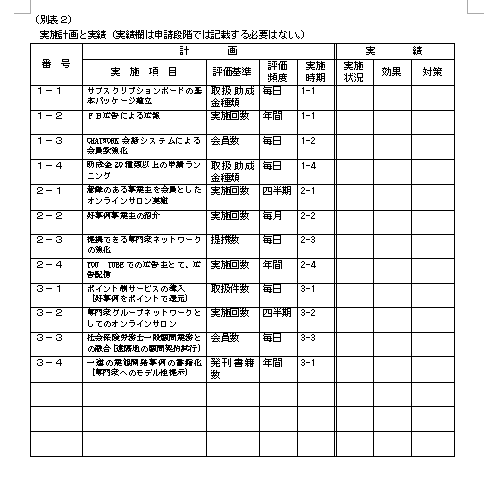
.gif)
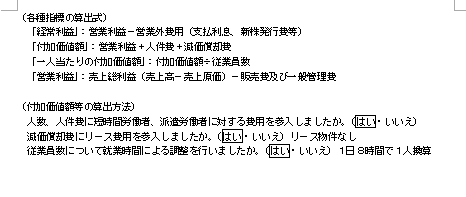
.gif)
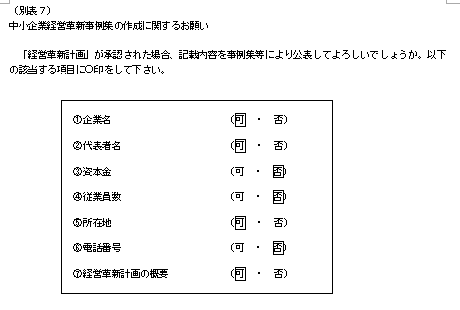
*経営革新法 個人 2020年2月作成
履歴との相関図
.gif)