
会社の目標をいつつくっていますでしょうか?
決算が出てからとなると、数か月遅れます。
そうなるとその間は目標なしに走ることになります。
正解は決算が閉まる2〜3カ月前に策定に入り、旧年度中に、決めてしまうということです。
その際に、当然その決算数値も、ベースになります。
いや、そこで、目標がそうなるという明確な因果関係を意識してください。
細かい決算修正の数値はこの際どうでもよいのです。
今回決算時からやってください。
年がゆくと
*結晶性能力 これまでの経験と近い状況で、獲得した知識を用いて問題を解決する知的能力 上がる↑
*流動性能力 これまでに遭遇したことのない状況で、既存の知識では解決できない問題を解決する能力
下がる↓ となります。
後段は変化対応脳能力のことです。
まわりの高齢経営者を見ていると、変化対応能力がないはまだましで、「あいつとは話もしたくない」など頑固になっています。
これではこの時代ダメなのです。変化に対応するにはストレスが溜まります。
これに耐えることこそ経営と言える時代なのです。
結晶性知能・流動性知能という場合もあります。
メルマガで「商材は予約がついてから作る」という言葉を紹介しました。
これは、情報商材の世界の言葉で労働工数の面と資金繰りの面からの言葉です。
このコラムでは前回先生業は、セミナー・研修・執筆・コンサルとあらゆる形に対応できなくてはならないと述べましたが、その準備の作業はオーダーがついてから動き出すべきです。
先にやっておくべきはそのジャンルのリスク研究だけです。
よく見かけるのは、準備作業ばかりで、クライアントとの接触を避けている人です。
次に流行ることはお客さんが一番よく知っています。
続く
「海外ビジネススタ―トの教科書」
〜マーケット変化と参入方法ケーススタディ〜
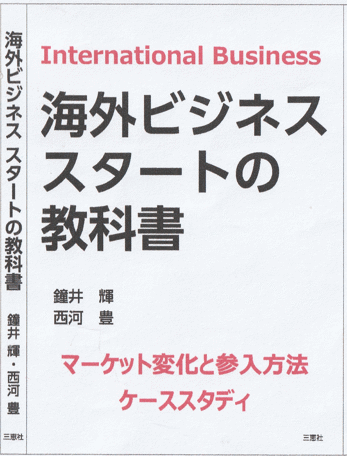
鐘井輝・西河豊 2,530円(税込み)三恵社
第Ⅰ章 近年のアジア市場の動向
第Ⅱ章 国際的ビジネス活動への参入
第Ⅲ章 インバウンドの動向と今後の対応
第Ⅳ章 フィジビリティ調査
第Ⅴ章 ビジネスの類型
第Ⅵ章 ビジネス参入時の異文化理解
第Ⅶ章 ビジネスの基本−世界標準(グローバルスタンダード)
第Ⅷ章 公的支援制度の活用
第Ⅸ章 先進事例紹介
200P以上あり、深く読める構成になっています。
申し込みはここ