
ものづくり補助金ブームが過ぎ、これから始まる助成金の波に対応すべく広報に努めているのですが、その普及度合いはまだまだです。
そこで、以前にも、ものづくり補助金で試行しましたが、助成金の各種類で、会社のパターンを類型化して
・どのような戦略で取り組むのか?
・申請書はどう書くか?
を事例と言うより小説化して説明して行きます。
これを読むと助成金の方は、申請はどの会社でも出来るのだなというのが理解できると思います。
***当社関連マニュアル***
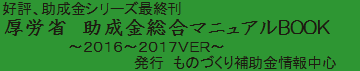
なども解説しています。
定価 2,000円
内容 PDFフアイル100ページ 問合せはここ
さて新コラムのスタートです。
重要度の高い順、取り組みやすい順です
御社の就業規則での服務規定は具体的に書けているでしょうか?
社内機密情報の持ち出しについてです。
多分、現在の最新ツールであるUSBなどの電子媒体にまで、表現は行き着いてないと思われます。
ここまで就業規則上、及んで置かないと「悪意があったとしても」、従業員からは「ついうっかり落としてしまった」など無過失を主張されるでしょう。
営業が外部に情報を持って出なくてはならない業種もあるでしょうから、上司の了解のもとなど、関所を複数設けておくことです。
次回は時間外労働を想定していない会社は最低・最悪!
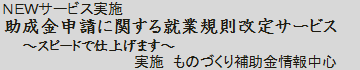
注)今般、提出が必要となった65歳超雇用推進助成金では業務委託契約書まで必要です。
金融と言う業態、あるいは金銭消費貸借契約を理解していただくために、面白い実験事例があります。個人同士が相対で、事業をするので、「事業資金を出資してくれ」というケースがあったとします。
その時、物価上昇や、金利の向上という背景がなかったとして、人は年何%の配当を用意するかという質問です。この質問に多くは5%程度と答えるとされています。人は直感的に投資リスクとそのリスクを持つリターンを5%とはじくのです。
これは、今や上場企業でも同じで調達面でもメリットはなくなりつつあります。
(参考:「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書 小宮一慶 PHP新書)
今、金融機関や保証協会でラインナップされている金利はそこまでいかないでしょう。
金融機関の貸付は投資行為ではありません。しかし、お金を貸すといった行為には似たところがあります。
この金利の差額をうめるのが、
①担保を求める。
②ビジネスプランを求める。
③複数の人間が稟議で慎重審査する。
という行為です。
ここで、①担保徴求について述べます。これは金融機関のシビアな側面としてよく取り上げらますが、事業者側から見ると、今まで事業で培った経営者の信用(個人保障、保証協会保証)、や不動産(抵当権、根抵当権)を金融資産が足りないときにその、調達の信用の補足として使えるというメリットもあるのです。
ここで担保の注意点は事業用資産を担保徴求されてしまうと事業の自由度が狭まりますので注意しましょう。
これで全国で、金融機関とお客さんが揉めています。これにも戦い方があります。
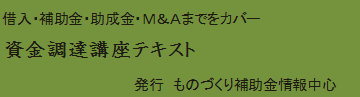
資金調達は何のためにするのか?それは資金を回すためではなく経営を持続・拡大するためです。
このテキストを読み経営が追い込まれる前に正しい資金調達法を理解しておなかいと企業低迷時には企業価値は驚く程のスピードで毀損し、打つ手も限られてきます。
アカデミックに勉強したい人にも読めるように構成しています。
定価 3,000円
発売 1月20日(金)
限定数 200部 問合せはここ
第2創業のアドバイスについて考え方を述べる。
前経営者の事業が好調、言葉を変えるとキャッシュフローを生み出している場合には、いかようにもプランニングできるので、問題にはならない。
また創業促進補助金における第二創業でも同じで、旧業態から新事業展開へのモデル化を図りたいと言う意図があるものと思われる。
この際に必要となるのは
・後継者の事業戦略のプランニング
・正しい事業継承知識と事業継承スケジュール
となるが、経営のゴーイングコンサーンの観点から重要なのは前者であり、果たして後継者の考えている戦略で経営が成り立つかということである。
そこで重要となるのが前経営者の事業とのシナジー効果であり、それがないならば、前経営者が事業清算して、後継者が創業者として創業した方が、キャシュフロー面からは楽に立ち上げることが出来る。
ここで、シナジー効果がないと分かっていながら事業継承すると言うことは、続いている事業体を破たんさせたくないと言う社会的責任からの事業継承となる。
しかし、そのような事情は、マーケットでは考慮されない。
またそのような思いだけで生き残れる経済状況でもなく冷静に考えるべき時代となっている。ただし、旧事業とのシナジー効果、すなわち旧事業の強みとなるべきコアな部分と言うのは事業の中に要るものにとってはかえって見つけにくいものであり、第3者のコンサルタントに相談するのはそれなりに意味がある。