
では、今後、厚生労働省の個別の助成金について見ていきますが、当社の方針として、厚生労働省のサイトを見れば分かるような事をそのまま載せるようなことは一切いたしません。
そんなもの(事実そのまま)は厚生労働省のサイトを見れば済むことです。巷にあふれる専門化のサイトはすべてそれです。
こういう補助金があります。こういう税制があります。それだけです。
なぜでしょうか?どうすべきかというアドバイス情報は全て有料から始めたいからです。
もうそんな時代ではないとの認識より、どうすべきかの情報まで含めどんどんFREEでOPENにしていきます。
では、分析の切り口です。
視点1 目的性は何なのか?
これはこれまで、解説したとおり
・雇用の促進 ・(キャリア)教育 ・労働環境・就業環境の向上
などですが、自社が、もともと伸ばしたいところであればベクトルが一致するのですから助成金を活用したほうが良いわけです。
視点2 資金使途はどうなるのか?
これも解説したとおり
・人件費の補填 ・教育費用の補填 ・コンサルテイング費用の補填
に加え、
・労働環境向上のための設備投資も可能なものもあるのです。
特に、商業・サービス業経営の方には、ものづくり補助金は当たりにくい構造があり、是非、検討してみてください。
視点3 戦略性は必要かなのか?
ここは少し解説します。
経済産業省の申請書は内容主義、厚生労働省は形式主義と定義しました。
しかし、近年、この経済産業省の内容主義⇒言い換えると戦略主義は他省庁にも押し寄せてきているのです。
それは、補助金・助成金の効果性が問われている昨今、戦略性のないところに効果なしという事がはっきりしてきているのです。
例えば「業務改善助成金」などです。
ですから、この部分は、代筆を頼むことなく、自社で考えて記入してください。
これは、こうなることは大いに予想されました。
かなり注意喚起したつもりです。
では、なぜ、採択率が低かったのかを説明します。
通常、人は何かを複数生産して行く時に、癖が出ます。
全ての癖を消すのは不可能です。
ものづくり補助金申請書に置き換えて言うとフオーマットにはめ込むと言う行為になります。
代筆作成で採択率が低かったというのは、そういう形跡がないか、県の中央会は全ての申請書をざっと見ているということです。
ざっと見ただけで、それは、一目瞭然になります。
当社に回ってくる申請書の中にも、これは代行作成(代筆)っぽいなというのがあります。
代行作成で料金払って更に当社へ依頼すると言うのは大変な費用のかけ方です。
というようなことはどうでも良いのですが、そういうケースでは当社はその癖を外すかに注力しています。
具体的に言うといかに素人が書いたように見せると言うテクニックを使います。
もし、このコラムを読んで、「これでだめだったんだ」と思われた事業所の方は着手金を無駄にされましたね。
事前にかなり言ったのに、遅かりしです。
今まで製作した中小企業関連の1,000本の動画より厳選セレクトした200本の動画を完全リンク!
ここで自分のペースで学んでください!
いままでの常識価格をぶち壊します!!
中小企業施策活用大学の受講の権利
補助金申請時の辞典としても役立つこと請け負います!
いままでの常識価格をぶち壊します!!
テキスト発送日 6月15日
予約可能!
限定:100人
受講料 1,000円
200動画を配備
テキスト 50ページ
レポート提出制度あり(任意)
動画リストの一部です。
問合せはここ
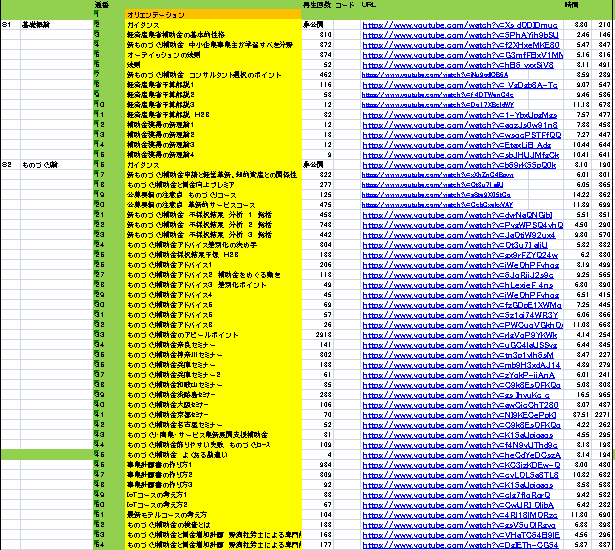
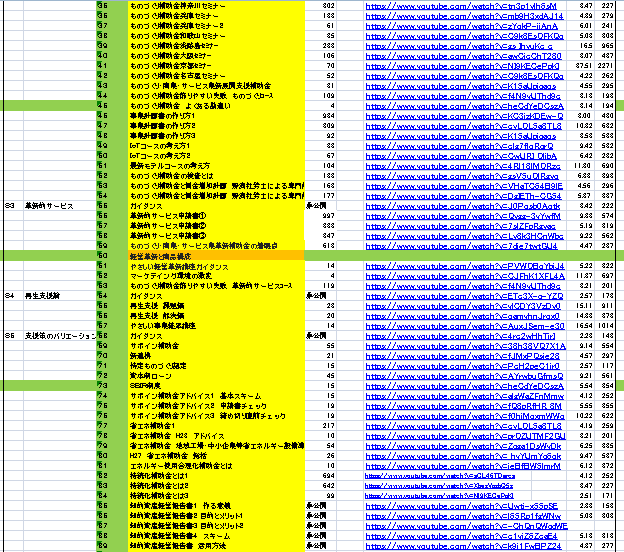
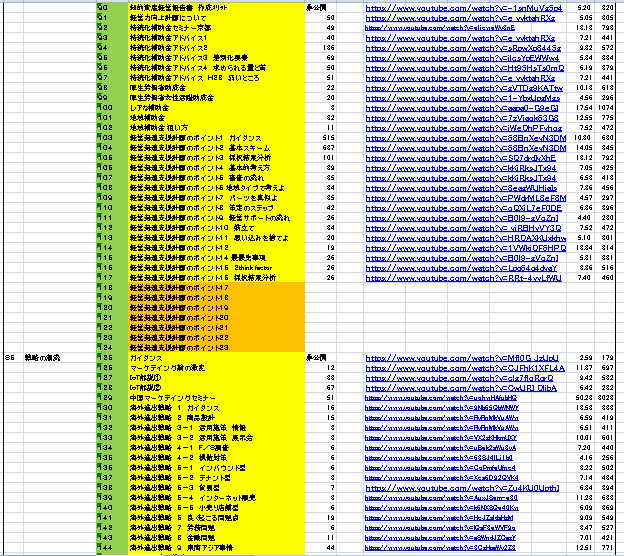
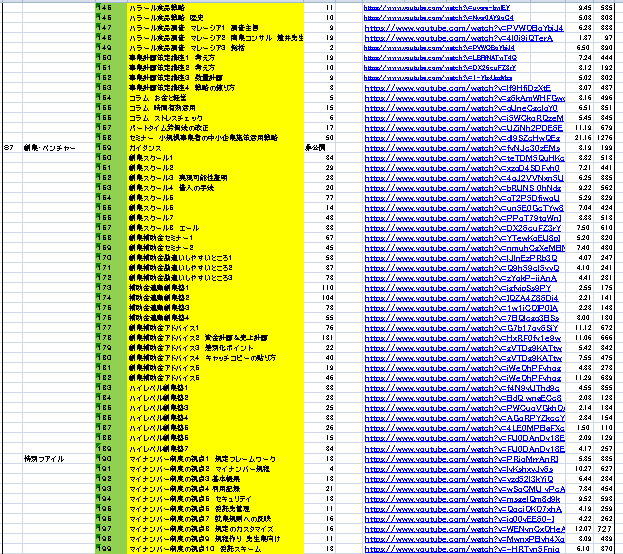
カリキュラムです。
第1章 中小企業施策の基礎理論
1−中小企業支援施策の体系
2−公平性の原則
3−内容主義
第2章 ものづくり概論
1−「もの」づくりへの志向
2−せばめる
3−スマイルカーブと戦略の潮流
第3章 経営革新概論
1ー経営革新法申請
2−プランを作る時の考え方
第4章 再生支援論
A.現状の再生支援の問題点
1−スキームの問題
2−内容の問題
B.実際に効果のある生き残り策
第5章 中小企業施策のバリエーション
1−特定ものづくり法認定
2−サポイン補助金
3−新連携
4−資本制ローン
5−SBIR制度
第6章 戦略構築の潮流論
1―IoT(Internet of Things)
2―海外マーケットの取り入れ
3―知財戦略
第7章 創業・ベンチャー論
1−創業の各段階で求められる能力
2−調達スキームをどう組むか
内容は全て経営に役立つ実学です。
問合せはここ